文化と共感が世界を動かす――大阪・関西万博「テーマウィーク」統括セッション

2025年4月13日から10月13日まで開催された大阪・関西万博で、ボストン コンサルティング グループ(BCG)は「テーマウィーク」を協賛した。「平和と人権」「食と暮らしの未来」など地球規模の8つのテーマについて有識者が対話し、解決策を探った。
最終セッションのテーマは「SDGs+Beyond:いのち輝く未来社会」。2030年のSDGs最終目標年を前に、人類が直面する課題を振り返り、「2030年以降の未来社会をどうデザインするか」を考える場として、『「いのち輝く未来社会」のデザインに向けた提言』というパネルディスカッションが行われた。
慶應義塾大学大学院教授の蟹江 憲史氏がモデレーターを務め、国連経済社会担当事務次長の李 軍華氏、国連ジュネーブ本部Beyond Lab ディレクター兼チーフキュレーターのオズゲ・アヤドガン氏、2020年開催のドバイ万博副会長のタレク・オリベイラ・シャヤ氏、慶應義塾大学教授で大阪・関西万博テーマ事業プロデューサーの宮田 裕章氏、大阪大学社会ソリューションイニシアティブ 特任研究員の佐久間 洋司氏、BCGのシンクタンク、BCGヘンダーソン研究所(BHI)の日本リーダーの苅田 修の6人が登壇した。
SDGsの進捗と、いま直面する「転換点」
セッションの冒頭で李氏は、最新の「SDGs報告書2025年版」から「SDGsのターゲットのうち、順調に進んでいるのはわずか35%。約半数は停滞し、18%は後退している」という厳しい現状を示した。気候変動、紛争、格差拡大といった複合的な危機が、世界の進歩を妨げていると指摘しながらも、李氏は「日本や世界各地で、市民・企業・行政が協働し、新しい解決策を生み出している。希望はそこにある」と述べた。

モデレーターの蟹江氏は、李氏の発言を受け、「グローバルな課題はローカルな実践によってしか解決できない」とし、自治体や企業、市民の協働の重要性を訴えた。
「文化」が社会にもたらす意義
その後、テーマウィーク全体の総括責任者であるBCGの苅田が、これまでの127人の登壇者による24 のプログラムを振り返り、「文化」「共感」「連帯」「共創」という4つのキーワードを提示した。「社会を変えるのは制度ではなく文化である」と語り、人と人が文化を通じてつながるときにこそ真の変革が生まれると強調した。蟹江氏は、「多くの人はSDGsに文化が含まれていないと考えがちだが、文化こそが社会を動かす手段であり、共感を生む装置だ」と述べ、苅田の意見に賛同した。慶應義塾大学教授の宮田氏は貧困の解消を目指して食料を与えるだけでは十分ではなく、人々が自ら働き、生きる意欲を持てるように支えることこそが重要であると述べた。そのうえで、医療や健康、そしてウェルビーイングをSDGsの目標に組み合わせることの意義を伝え、「病気を治すことだけでなく、自然で健康的な暮らしを支え、そこから幸福を生み出すことが、真のウェルビーイングにつながる」と語った。
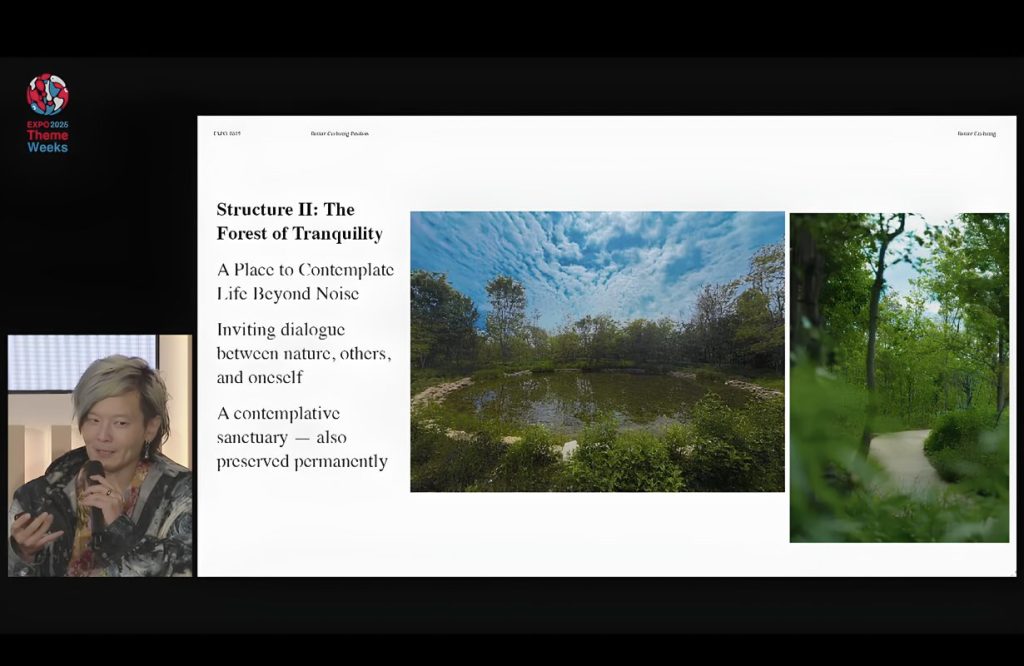
未来は待つものではなく、選び・創るもの
大阪大学の佐久間氏は、世界20か国以上から集まった120人を超える若者たちとともに未来を構想した経験を振り返りながら、「未来は待つものではなく、選び・創るもの」と強調。AIなどの先端技術を活用した平和構築のアイデアを紹介しつつ、「革新的な発想であっても、世界全体で共有し実現することの難しさも痛感した」と語った。続けて、「違いを起点に共通点を見出す」ことの重要性に触れ、「同質化ではなく、違いから出発すること。その違いこそがイノベーションの源泉だ」と述べた。
2020年開催のドバイ万博副会長のシャヤ氏は、「速く行きたければ一人で行け。遠くへ行きたければ仲間と行け」というアフリカのことわざを引用し、現代はスピードと連帯の両立が求められる時代だと語った。また、「すべての国が同じペースでSDGsを達成することはできない」とした上で、目標ごとのタイムライン設計と、加速をもたらす技術導入の重要性を指摘した。
2030年に向けた3つのS
国連ジュネーブ本部Beyond Labのアヤドガン氏は、「これからの社会はウェルビーイングを中心に再設計すべきだ」と語った。そして、「経済の枠組みそのものを見直す時期に来ている」と続けた。これまでの社会は成長やGDPなどの数字に偏りすぎていたが、これからは人や自然を含めた本当の豊かさをどう測るかが問われるという。アヤドガン氏は、「未来をつくる責任は誰か一部の人ではなく、私たち全員にある」と主張。国や企業だけでなく、市民や地域社会も含めて、それぞれがウェルビーイングを基軸にした社会をどう築くかを考えることの重要性を説いた。

セッションの最後では、李氏が「Share(共有)、Shape(形成)、Shine(輝き)」の三原則を提唱した。これは知識や経験を共有し(Share)、多様な主体が協働して社会を形成し(Shape)、その成果が人々の幸福として輝く(Shine)という行動指針である。李氏は「大阪・関西から発せられたこの理念は、分断の時代における希望の光であり、世界が共に歩む羅針盤となる」と締めくくり、聴衆の大きな拍手を受けた。
セッションの様子は、テーマウィーク公式ウェブサイトでアーカイブ配信する予定だ。




